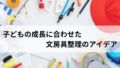「また今日もプリント?」「この作品、捨てられない…」
子どもが学校や園に通い出すと、嬉しい反面、持ち帰ってくるおたよりや作品の量に頭を悩ませてしまうこと、ありますよね。
私自身も最初のころは、「思い出だから」「とっておこう」と、どんどん取っておいてしまい、いつの間にか引き出しや棚がパンパンに…。
でも、よく見ると、「すでに期限切れのプリント」や「誰が描いたか分からなくなった絵」も混ざっていたりして、反省しました。
この記事では、そんな**整理に悩む親御さんのために、実際に家庭でできる「学校プリント&作品整理術」**をお伝えします。
必要なものは無理なく残し、大切な思い出もちゃんと守れる。そんな仕組みを一緒に作っていきましょう。
なぜ学校のプリントや作品はたまりやすいの?
毎日の配布物が地味に増える
学校生活には、保護者向けの案内やおたよりがつきもの。
遠足のお知らせ、健康調査票、給食の献立、保護者会の案内…など、内容も形式もバラバラです。
1日1〜2枚程度だとしても、週に10枚前後。1か月で40枚、1年なら約500枚近くにもなる計算です。
そのほとんどが「とりあえず取っておく」になってしまうと、気づけば山積みに。
しかもそれが、兄弟姉妹それぞれにあるとなれば、もう大変…!
「捨てにくい」「思い出」として残したくなる心理
子どもの描いた絵や手紙、がんばって書いた作文、初めてのテスト100点…。
どれもが愛おしく、簡単に捨てられるものではありません。
特に低学年の頃は、「何でもかんでも宝物」に見えてしまいますよね。
でも、全部取っておくわけにもいかない。そんなジレンマを抱えがちです。
整理の基本は「分ける」と「ルール化」
まずは3つに分類【必要・保留・処分】
どんな整理も、まずは「仕分け」から始まります。
わが家では、以下の3つの分類に分けて考えるようにしています:
-
必要(しばらく残す)…学校行事や重要なお知らせ
-
保留(迷っている)…作品、テスト、思い出系
-
処分(役目を終えた)…過去の献立表、連絡済みの案内
迷うものは「保留」ボックスに一時保管し、定期的に見直すことで、ムダに溜めこむことを防げます。
1年を通して見直すタイミングの決め方
おすすめの見直しタイミングは以下の3つ:
-
学期末(通知表と一緒に見直す)
-
長期休み前(夏休みや冬休みに整理)
-
年度末(新学年を迎える準備として)
このサイクルを意識するだけで、プリントや作品が自然と「回転」するようになります。
また、見直しのときに子どもと一緒に判断する時間を作ると、「これはもういらないかな?」という声も聞けて、親子で納得しながら進められます。
プリント類をスッキリ保管するアイデア
無印や100均のファイル活用術
A4サイズ対応のクリアファイルやドキュメントボックスは、プリント整理の必須アイテム。
とくにおすすめなのが、以下の組み合わせ:
-
月ごとのインデックス付きクリアファイル(100均でOK)
-
無印良品のポリプロピレンファイルボックス
-
カラー別に分けて家族ごとに管理できるバインダー
これらを「1人1ファイル制」にしておくと、子ども自身もどこに何があるか分かりやすく、親も急な提出書類にも焦らず対応できます。
月別・子ども別に分けて管理する方法
わが家では「子ども別にボックスを用意し、その中を月別に分ける」方法を採用しています。
たとえば:
-
息子(青いファイル)→ 月ごとにインデックスをつけて分類
-
娘(ピンクのファイル)→ テストとおたよりで更に分けて保管
こうすることで、「3ヶ月前の行事案内、どこだっけ?」という時もすぐに見つかりますし、家族みんなが「自分のものを自分で管理する意識」も芽生えてきます。
作品整理は「写真保存+選抜制」がカギ
残す作品の基準を決めるコツ
作品の整理で迷ったときは、「思い出フィルター」を通すことが大切。
-
家族のエピソードがあるもの
-
成長を感じられる作品
-
子どもが自分で「取っておきたい」と言ったもの
これ以外のものは、「写真に残してOK」とするルールにしておくと、無理に捨てた感覚にならずに済みます。
写真アルバムやデジタル整理も活用しよう
最近は「子ども専用フォトブック」を作る家庭も増えています。
アプリで簡単にアルバムが作れるサービス(しまうまプリント、ノハナなど)を使えば、手間もコストも最小限。
さらに、GoogleフォトやDropboxなどのクラウドサービスを使えば、祖父母と作品をシェアすることもできます。
子どもと一緒に整理することで得られるメリット
「選ぶ力」を育てるチャンスに
整理は、「捨てること」ではなく「選び取ること」。
子どもに「どれを残す?」「これはなぜ大事?」と問いかけることで、選択力・思考力・自己決定力が自然と育まれます。
これは、将来的に自分の持ち物を管理したり、片付けたりする上でもとても大切な力になります。
作品を見返すことで家族の会話が増える
「これ描いたの、覚えてる?」「このとき、こんなことあったよね」と振り返ることで、家族のコミュニケーションが自然と深まります。
モノを整理することは、思い出を共有する時間にもつながるんですね。
我が家の整理ルール(体験談)
子どもとの話し合いでルールを決めた話
わが家では、小学2年の息子と、「作品は1学期に3つまで選ぶ」というルールを一緒に決めました。
最初は「全部とっておきたい!」と言っていた息子も、「じゃあ、どれが一番思い出に残ってる?」と一緒に話すうちに、「これはすごくがんばったから」と、自分で選べるように。
親が一方的に決めるのではなく、「一緒に考える」ことで、子どもも納得してくれるようになります。
実際に使っている収納アイテム紹介
以下は我が家で実際に使っている便利アイテムです:
-
無印良品|ポリプロピレンファイルボックス
→ 安定感があり、積み重ねても倒れにくい。リビングに置いてもスッキリ。 -
セリア|A4書類用ワイドケース
→ 月別、種類別に分けて入れられる。ラベルでカスタムも◎ -
IKEA|TJENAボックス
→ 作品や立体物の一時保管にピッタリ。フタ付きで見た目もキレイ。
まとめ|思い出を大切にしながらスッキリ暮らそう
子どもが一生懸命取り組んだプリントや作品は、確かにどれも大切。
でも、全部を取っておこうとすると、管理しきれず、大切なものほど埋もれてしまうことも。
大切なのは「全部を残すこと」ではなく、「どれをどう残すか」を親子で考えること。
そして、整理という作業を通じて、子どもとの対話や成長の記録が自然と生まれてくるのだと思います。
ぜひ今日から、わが家に合ったプリント&作品整理のスタイルを、無理なく、楽しく見つけてみてくださいね。